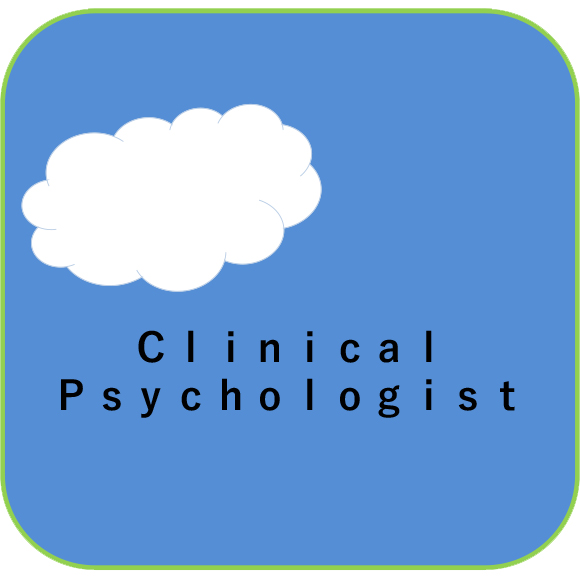[起立性調節障害]の質問に答えてみる
心理・精神科臨床投稿
2025.11.24
こころの病か、からだの病か のさまざまをみてみる
事例への助言を求められる機会の中でちょっと気づいたことがありました。
養護教諭の先生方との会では、実際のケースを通して以下のような理解が共有されていると感じます。
しばしば登校の難しさが生じてきたときに、頭痛などの症状を訴えたり、起床できなく(しなく)なったりがみられ、小児科や内科などを受診されたときに よくいわれてくる名称の印象が少なくない。
もちろん行うべき検査を実施し、データもそれを裏付けると思ってよいものの時もあれば、検査らしきものはしていないらしいこともある。
たとえば進級や進学で登校がスムーズ(順調))になると、症状が「改善」したか否かにかかわらず、その訴えは消失あるいは減少することも珍しくない。
そのようなことから、もちろん重篤なOD症状を有するケースもないわけではないし、主観的には苦痛を感じる症状があるといえるのかもしれないが、いっぽう安易に”なにかしら固定的な疾患にり患した、とでもいうようなとらえ”をしないで置く姿勢も必要。
これに対して このようなケースに出会ったことのない方々は
なにかしら明確な身体的な背景がある、疾患単位として明瞭なものとしてとらえている と感じます。
ときにはなにか難病ででもあるようなイメージで・・・。
実際には、ある名称をもった「疾患」が存在するのかどうかについての
議論が続いているもの、
存在は認められているもののその診断の基準や方法の妥当性を巡って、確定的ではないもの
などなど とくに児童思春期・青年期に関連しているものは少なくない といえるでしょう。
身体疾患の知識に弱点のある心理職はこのような「疾患」についての基本的な理解は押さえておきたいものです。
そのような点で、以下の書籍を手元に置いておいてはどうでしょう。
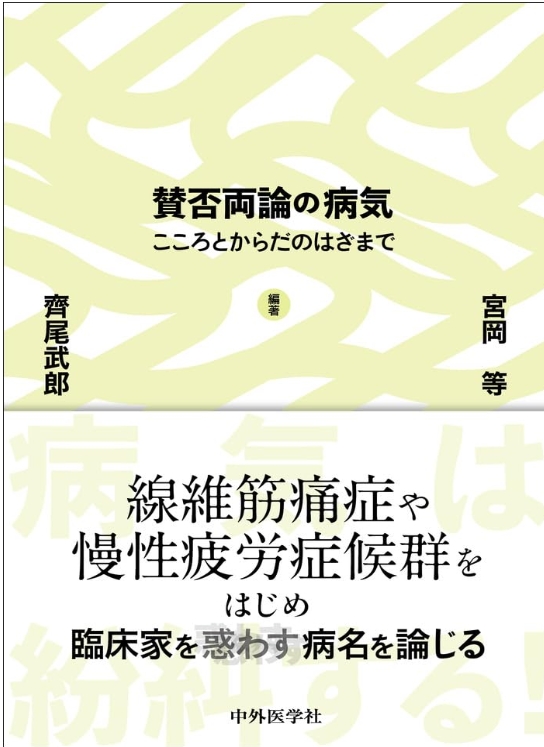
Contested illness: 論争中の病 疑義の呈された病 認められぬ病 などと訳される。
本の帯の後ろ側を引用します。(ちなみにこの帯という存在は、日本の書籍にしかないようです)
1)特異的な身体所見が乏しく、疾患自体の存在に様々な議論がある病態
本書の帯より
2)中核には確かな身体疾患あるいは病態があると一般に認められているが、
経過中にその疾患名では説明しきれない症状が目立ってくる病態
3)疾患名自体に確かな身体所見がないという意味が含まれる病態
「起立性調節障害」の定義の混乱や、日本特有の事情も関係しているようです。
” 本邦におけるODの疾患概念は、身体主訴を持つ不登校児の急増を契機とし、主として小児科領域で発展してきた。国外では自律神経や免疫学的な要因を中心とした成人の身体疾患としてODを捉えているのに対して、本邦では心理社会的因子の関与によって発症・悪化する心身症としての認識のほうが優勢である。”
本書 p121
” ガイドラインに明記されているとはいえ、ODに対する適切な検査や診断、治療が広く実施されているとは言い難い。(中略)身体愁訴(自覚症状)だけでODと診断され、十分な検査もなく体裁を整えただけの治療が長く続けられてしまうと改善は難しい。(中略)それでもまずは生理学的機能を丁寧に評価することに留意し、「気持ちの問題」を性急に前景化させないことが大切である。”
本書p129
このほか
慢性疲労症候群
線維筋痛症
脳脊髄液減少症 などとともに
筋緊張性頭痛と片頭痛
HPVワクチン接種後に生ずる多彩な症状
機能性高体温症/心因性発熱
なども挙げられており、その存在を認めるにあたってどのような対立点があるのか、最新の研究や到達点はどのようなものか などをみることができるでしょう。全部を読んでも身体疾患の知識や検査のことなど、知らないことが多いと感じるかもしれませんが、ケースに出会ったときに「両論併記」であるこの本に当たることにする、もよいのではないかと思います。