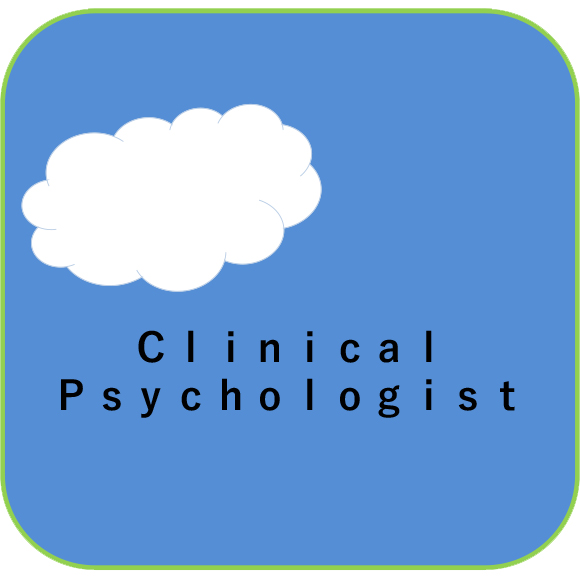「場面緘黙は不安症です。」
場面緘黙
2024.02.01
不安症の治療は不安の特性および不安症の発生機序と治療のことを理解した精神科医や臨床心理士の領域です。(丹明彦先生 Xより)
前回ご紹介した 丹明彦先生から、Xおよびご著書の引用・ご紹介をご快諾いただきました。先生のご提案で、一部句読点そのほか修正させていただいております。
「場面緘黙は不安症です。不安症の治療は不安の特性および不安症の発生機序と治療のことを理解した精神科医や臨床心理士の領域です。統合失調症の緘黙症状を知らないと危険な治療が横行してしまいます。」
Apr 14. 2023
そうですね!場面緘黙が知られるようになってきた分、その分、そうではないものが場面緘黙であると誤解されないようにすることも重要になってきたわけです。たとえば カタレプシー(catalepsy)を「ああ、それ緘動だね~」とかいわれて様子見されてしまう可能性。ここは迂闊でした!!これまで逆ばかりだったので…。
やはり「場面緘黙かな」と学校で思われたお子さんはSCにご相談いただきたいものです。学校に来ているし、迷惑かけてないから、と相談につながっていないお子さんも多いです。そしてSCは自分ではよくわからなかったら、あいまいに答えて終わらせず、臨床のわかる先輩なりに助言を得てください。
構造化されたクリニカルな場での臨床が原則。これが世界的基準です。
Apr 14 . 2023
そうなんです。「エライ人が言ってたから」じゃなくて「それは世界標準ですか」を問う姿勢が、援助をする人には必須なのではないでしょうか。なにぶんわたくしのような田舎の一介の心理職よりも、教授などと名の付く方のおっしゃる言葉のほうがアカデミックと聞こえるのも当然でしょう。別段私と比較していただかなくてよいので、それは「世界基準なのか」を問えばいいだけの話です。

そんなことをしなくとも「そのひとの主張・方法は子ども、家族を理解しようとする姿勢があるか」を問うだけで充分かもしれません。「そこに”愛”はあるんか」(某CM)ほんとにその言葉のままです。
「子どもの理解は、子どもが何を思い、何を感じ、何を考え、何を願っているのかを知る、知ろうとすることからしか始まらないよ。それを抜きにして「子どものことを知るために、特性や取り扱い方を知るために、検査」って何を知ろうとしているのか?人は機械ではない。」
「決して検査の意義を否定しているのではありません。むしろ知能検査には詳しいですし、院でも教えていましたから。当センターでも積極的に行っています。子どもを大人の都合で勝手に何かに括らず、まずは言い分をしっかりと聴くことから始めてほしいのです。」
Apr 6. 2023
怪しげな説法を語る教祖をあがめてしまい、子どもを生贄にしていないでしょうか・・・。
傷ついた保護者や子どもの怒りや悲しみが、その事態をまったく変えることにつながっていないことは不思議でなりません。
場面緘黙のお子さんが療育に支援を求めることが増えているが、改善しないだけでなく悪化する例も少なくない。不安の取り扱いや、社交不安の特性を併せ持つことを知らないことが何よりの原因。アプローチがそもそも全然異なる。不安症の治療経験のある臨床心理士につながることが一番大事。
Apr 14. 2023
「HSP」でも問題になっていますが、なにかしら新しい言葉は知られてくるとかならず「○〇専門カウンセラー」「○〇克服講座」などが現れ、詐欺的商法や宗教勧誘が出現します。「かんもくネット」でも注意喚起がでておりました。
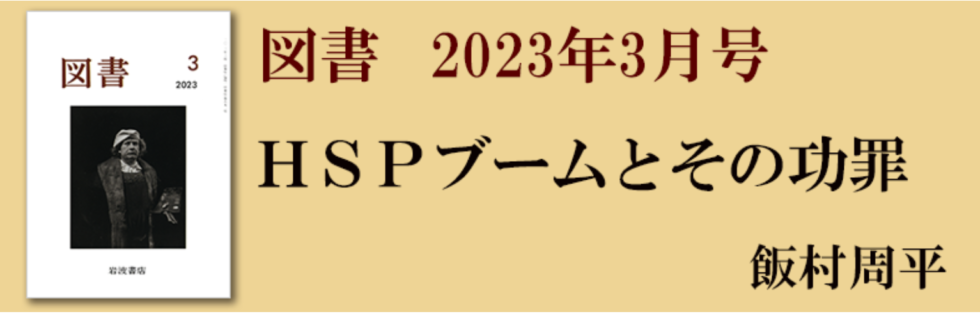
そこまで怪しくはないにしても「プレイセラピー」には心理職であっても慎重さは不足しているように思います。とくに箱庭療法の安易な導入には反対です。行うならば、適応かどうかの判断から導入、経過の見立てまできちんと指導を受けながら行うべきです。
臨床の経験のない、心理職でもない方が、適応すべきではないと思われる対象に対して、「箱庭でもやってみようと思ってます」とおっしゃっていたなどという話も聞こえてきて・・・恐ろしいことだと思いました。本来はそんなに簡単に入手でいるものですらないので・・。それこそ「箱庭の世界基準で言えば」。
なにをしたらいいかわからないときほど「なんとなくプレイ」をやって時間をやり過ごしたくなります。SCでもそうでしょうね。なぜその道具を使ったのかな?子どもはそれをどう体験したのかな?
なにをしたらいいかわからなくて「遊び」をしたとしたら子どもがどんなに楽しそうだったとしても、それは「あなたのための時間」。
箱庭の世界基準 の考え方については
戸塚悌子先生「箱庭療法」にむけて(討論の広場)精神療法 28巻2号 2002年 をご一読ください。
ちょっと横道にそれてしまいましたが、丹先生のご投稿はうなづくことばかり(年配の心理職も少しは役に立つよというメッセージや、検査のSV受ける前に手引き読もうねとか…)でご紹介しきれませんのでぜひお読みくださいね。
プレイセラピーのご本も出されています。
先生は大学をおやめになって相談室を運営されています。